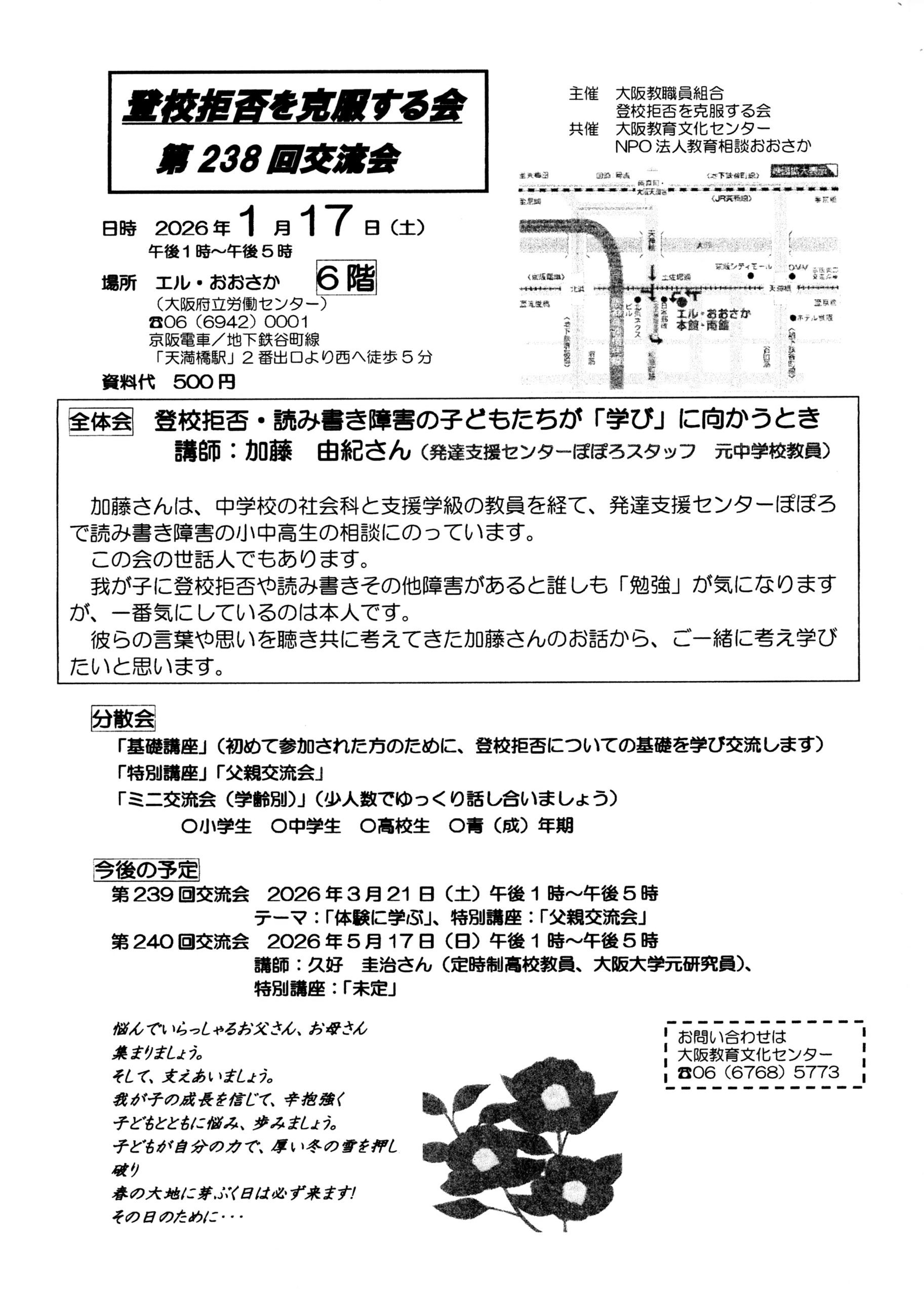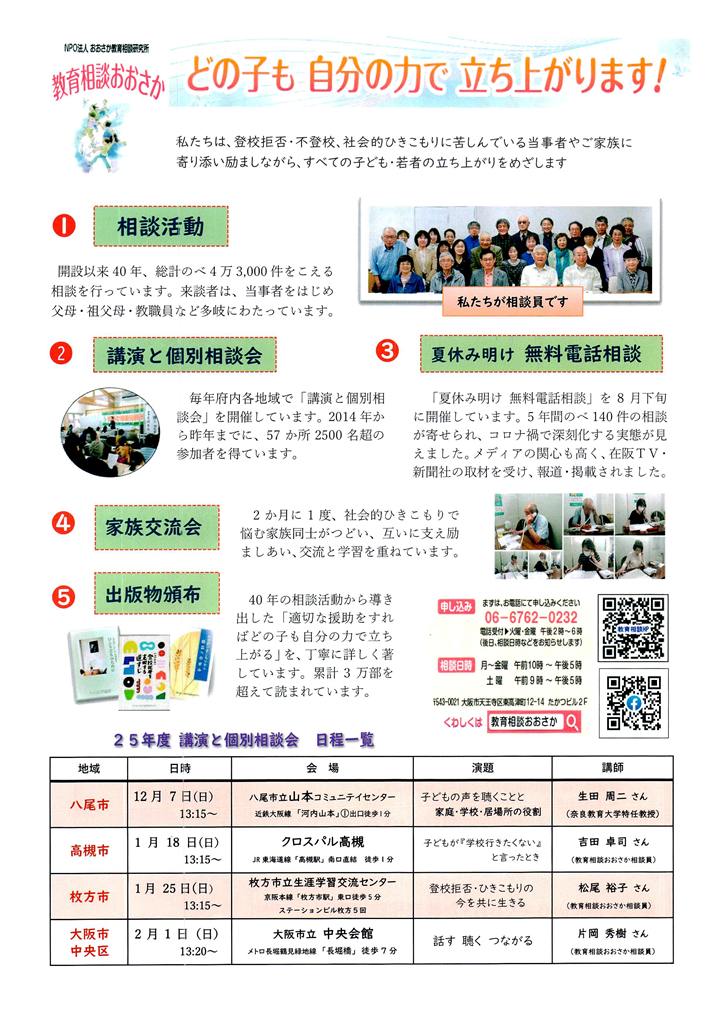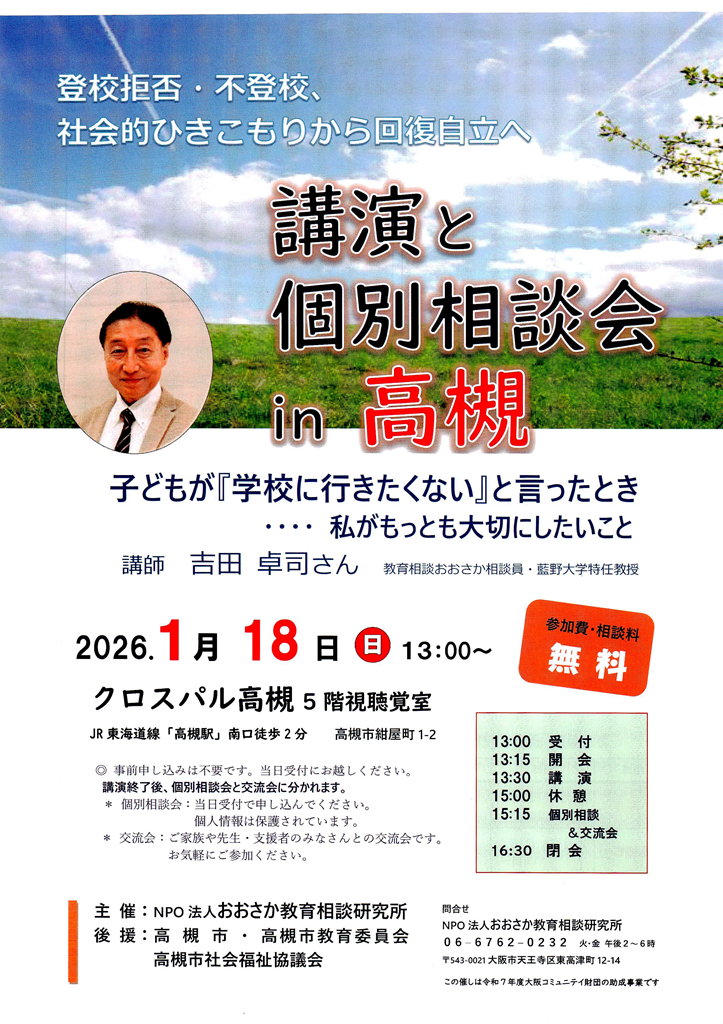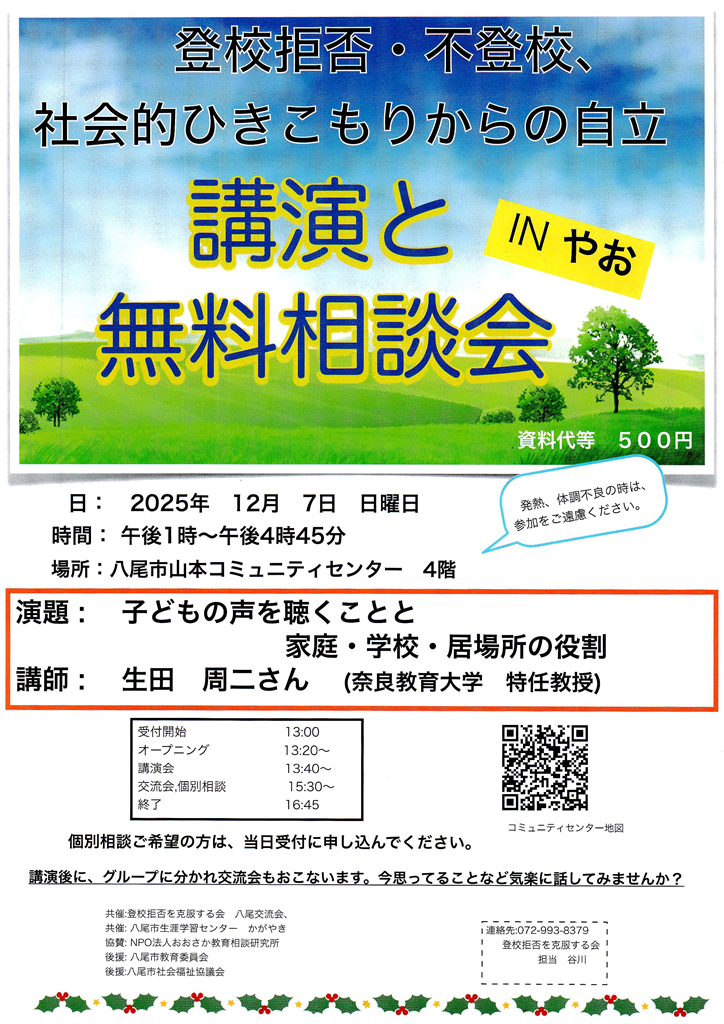各地域交流会の連絡先など詳しいことは、NPO教育相談おおさか または 大阪教育文化センター にお問い合わせください。
< 第196回 豊能地域交流会 >
1月12日(月祝)午後1時30分~5時
会場/豊中市立地域共生センター3F(岡町駅から東へ300m)
相談員/村上さん
参加費/500円
< 第170回 いばらき交流会 >
2月21日(土)午後1時30分~4時30分
会場/茨木診療所3F 中会議室
参加費/300円
< 第17回 吹田地域交流会 >
2月22日(日)午後2時~4時30分
会場/吹田市立山三公民館(阪急バス「亥子谷」)
参加費/100円
< 第200回 北河内地域交流会 >
2月8日(日)午後1時~5時
会場/さだ生涯学習センター
相談員/石野さん
参加費/500円
< 第93回 淀川交流会 >
2月21日(土)午後1時~5時
会場/三国社会福祉会館(阪急三国駅)
相談員/竹内さん
参加費/500円
< 第182回 城北地域交流会 >
2月1日(日)午後1時30分~
NPOおおさか教育相談研究所の講演と個別相談会に合流します
会場/大阪市中央会館
参加費/無料
< 第186回 大阪市南部地域交流会 >
2月15日(日)午後1時30分~5時
会場/あかつき保育所(JR「寺田町」下車 北出口15分)
相談員/馬場野さん
参加費/500円
< 第188回 東大阪地域交流会 >
2月8日(日)午後1時~5時
会場/東大阪市立市民多目的センター(近鉄奈良線永和駅下車北へ2分)
相談員/高砂さん
参加費/500円
< 第195回 八尾地域交流会 >
2月8日(日)午後1時30分~4時45分
会場/八尾市山本コミュニティセンター かがやき
内容/お父さんの体験談
参加費/500円
相談員/馬場野さん・竹内さん・東さん・山田さん・椿山さん
< 第310回 堺地域交流会「堺まったりカフェ」 >
2月1日(日)午後1時30分~3時30分
NPO法人堺子育て・教育ネットワークと合流します。
会場/堺教育会館・堺教組(南海堺東駅)
相談員/森下さん
参加費/無料
連絡先/堺教組 ℡ 072-221-1717
< 第154回 泉北ニュータウン地域交流会 >
2月22日(日)午後1時15分~4時30分
会場/堺市立南図書館3F
参加費/500円
< 南河内地域交流会 >
当分お休みします。
< 第193回 泉州地域交流会 >
12月21日(日)午後2時~5時
会場/岸和田市立春木市民センター(南海春木)
相談員/片岡さん
参加費/300円
< 第210回 奈良県登校拒否を克服する会 >
2月21日(土)午後1時15分~午後4時30分
会場/奈良市保健所(はぐくみセンター)
内容/交流会
参加費/500円
< 200・201回 神戸地域交流会「ゆずりはの会」>
1月24日(土)午後1時30分~4時30分
3月8日(日)午後1時30分~4時30分
会場/神戸市立婦人会館
相談員/村上さん
参加費/500円
< 第150回 尼崎地域交流会「あんだんての会」 >
2月22日(日)午後1時~5時
会場/尼崎市立 立花北生涯学習プラザ(阪急塚口駅から徒歩7分)
相談員/片岡さん
参加費/500円
< 第136回 宝塚地域交流会「宝塚のつどい」 >
2月21日(土)午後1時30分~5時
会場/宝塚市立男女共同参画センター・エル学習室2(阪急宝塚駅ソリオ2)
相談員/村上さん
参加費/500円